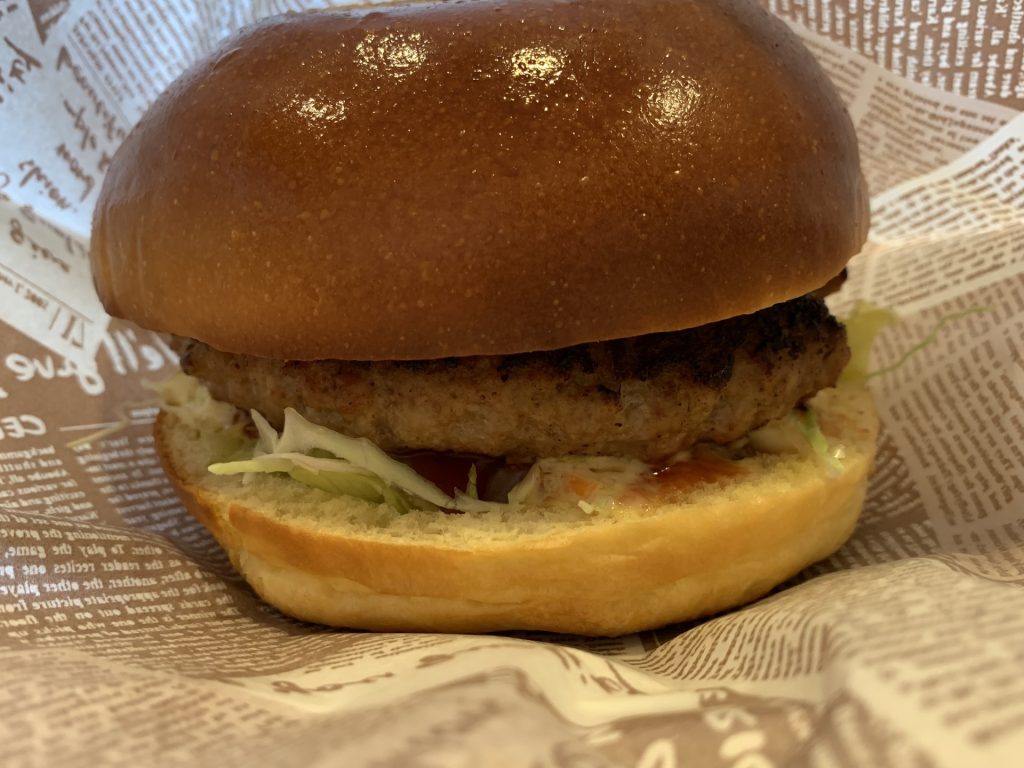井草八幡宮(いぐさはちまんぐう)は、東京都杉並区善福寺にある神社です。
井草八幡宮
井草八幡宮は、善福寺川を見下ろす台地、青梅街道と早稲田通りの交差点にある、広大な敷地面積を誇る神社です。都内では4番目に広く、境内は厳かな雰囲気に満ちています。明治時代までは、昔の地名から「遅野井(おそのい)八幡宮」と呼ばれていました。
 井草八幡宮 大灯籠
井草八幡宮 大灯籠
井草八幡宮には、入口が2箇所あります。井草八幡前交差点側の北参道には、木々の緑に映える朱色の大鳥居と、高さ9メートルに及ぶ威風堂々とした佇まいの大灯篭があります。大灯篭を眺めながら、ゆっくりと参道を歩けば、心が洗われるような気持ちになります。
 井草八幡宮
井草八幡宮
大鳥居は、東日本大震災で破損した石鳥居に代わり、2013年に建立されました。屋根は銅板葺きで八畳分の広さがあります。
 井草八幡宮
井草八幡宮
もう一つの入り口は、青梅街道沿いにあります。1957年建立の大鳥居があり、そこから直線距離200メートルの東参道が伸びています。
 井草八幡宮
井草八幡宮
東参道は、初詣や例大祭の時期には、多くの人で賑わいます。例大祭の時期には、200軒以上の夜店が並びます。3年に一度行われる神幸祭や、5年に一度行われる流鏑馬神事には、活気に満ちた雰囲気となり、日本の伝統文化を感じられる貴重な場となります。
 井草八幡宮 楼門
井草八幡宮 楼門
楼門は、鉄筋コンクリート造りで1971年に作られました。随神が一対納められています。
 井草八幡宮 楼門
井草八幡宮 楼門
井草八幡宮の楼門は、左右両側に各町会の神輿庫がある点が特徴です。これは、それだけ多くの町会が神輿を所有し、盛んに祭礼を行っていることを示しています。
 井草八幡宮
井草八幡宮
井草八幡宮の創建年代は不明ですが、1190年代ではないかとされています。かつて社前には、1193年に植えられた赤松と黒松がありましたが、1本は明治初年に、もう1本は1973年に枯れてしまいました。
 井草八幡宮
井草八幡宮
枯れた松の根の一部は、拝殿の回廊に「ついたて」として飾ってあります。
 井草八幡宮 頼朝公お手植えの松((よりともこう おてうえのまつ)
井草八幡宮 頼朝公お手植えの松((よりともこう おてうえのまつ)
境内には、2代目の松が「頼朝公お手植えの松」として植えられています。2代目の松は、頼朝とのつながりを象徴する貴重な存在として、多くの参拝客の注目を集めています。
 井草八幡宮
井草八幡宮
善福寺池が湧水だったことから、井草八幡宮の周辺地域は古くから人々の生活拠点でした。そのため、境内地からも縄文時代の土器などが発掘されています。井草八幡宮には、郷土資料などの文化財や昔の生活用具を展示した民俗資料館があります。
 井草八幡宮
井草八幡宮
井草八幡宮の境内は、厳かな雰囲気と自然豊かな雰囲気が調和した、とても素敵な場所です。本殿の周りには透塀(隙塀)があり、神聖な空間を守ることで本殿の神秘性を高め、荘厳な雰囲気を演出しています。
 井草八幡宮 本殿
井草八幡宮 本殿
本殿は、1974年築のコンクリート製の権現造りの覆殿です。1664年に、改築された「朱雀(すざく)の本殿」と呼ばれる一間(1.8メートル)四方の朱漆りの杉並区最古の木造建築の本殿が覆殿内に納められています。
 井草八幡宮 文華殿 (ぶんかでん)
井草八幡宮 文華殿 (ぶんかでん)
文華殿は、当初、神輿庫して設計されていましたが、今では付近で出土した土器、武具、奉納額を収蔵しています。現在は、楼門が神輿庫として利用されています。文華殿は、例祭日(9月30日から10月1日)に無料公開されています。
 井草八幡宮 招神殿 (しょうしんでん)
井草八幡宮 招神殿 (しょうしんでん)
招神殿は、1813年に造られた元拝殿です。現在は祖霊舎として戦争で亡くなった方を中心に祀られています。
 井草八幡宮 神楽殿 (かぐらでん)
井草八幡宮 神楽殿 (かぐらでん)
神楽殿は、舞台だけのものから橋掛かりのあるものへと改築されました。神楽殿では、能や狂言などの舞台などが執り行われます。
 井草八幡宮
井草八幡宮
井草八幡宮は、歴史、文化、自然を満喫できる魅力的な神社です。ぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。
機会があれば、再度来てみたいですね。
それでは、また。