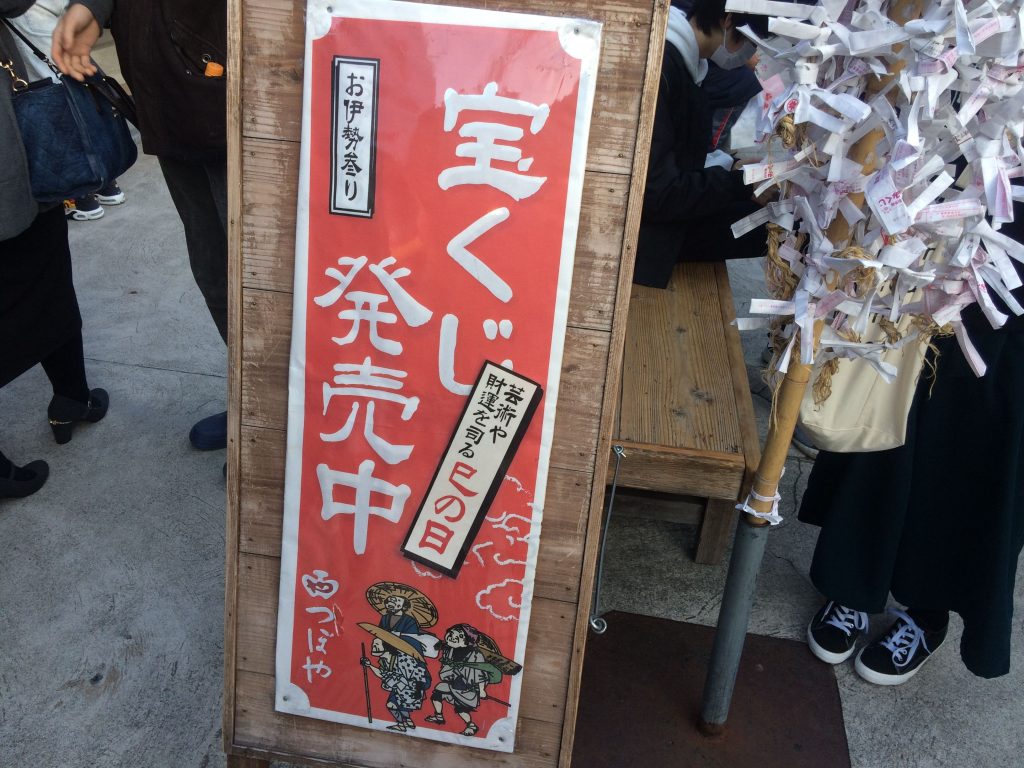伏見稲荷大社は、京都市伏見区深草にある神社です。

「お稲荷さん」と親しまれる伏見稲荷大社は1300年以上の歴史を誇り、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮です。
商売繁昌や家内安全のご利益があるとされ、一年を通してたくさんの参拝者で賑わっています。
大鳥居をくぐり抜け、長い参道を進んでいきます。

二番鳥居の先に見える楼門は存在感がありますね。

楼門は伏見稲荷大社の顔でもあり、重要文化財にも指定されている貴重な建物なので、記念写真を撮るには絶好のスポットです。
お正月なので楼門がライトアップされ、幻想的な雰囲気に包まれています。

伏見稲荷大社の狛狐は、稲穂、巻物、鍵、玉を口に加えていて、格好もさまざまです。
稲穂は五穀豊穣、巻物は知恵、玉は稲荷神の霊徳の象徴、鍵は稲荷神の御霊を身につけようとする願望だそうです。
玉と鍵は陽と陰、天と地を示すもので、萬物は、この二つの働きによって、生成し化育する玉鍵の信仰が伏見稲荷大社には、あるそうです。

外拝殿と本殿の裏手には、伏見稲荷大社の最大の見どころ、朱塗りの美しい千本鳥居がありました。
日中だと映えるスポットですが、夜間に来ると少々怖い場所でもありますね。
朱塗りの鳥居がズラリと連なる光景は圧巻です。

大きな鳥居の先には、小さな鳥居がありました。
千本鳥居は、願いごとが「通るように」または「通った」というお礼をこめて、鳥居を奉納する習慣が広まったことによるものだといわれていて、参拝者の思いがこもった鳥居は、いまでは境内全域に約1万基が並ぶそうです。

今日は1月2日ということもあり、千本鳥居を抜けてたどり着く奥社奉拝所の右奥のおもかる石の前には行列ができていました。
おもかる石は、持ちあげた時に、その重さが自分が予想したよりも軽いと願いが叶い、予想したよりも重いと、その願いを叶えるには一層の努力が必要、ということだそうですが、想像していたのと同じ重さに感じました。

もう22時になり、先に進んでも暗くて何も見えないので参拝を終了しました。
お守り授与所はすでに閉店していて、境内の人影も少なくなりました。

伏見稲荷駅 
稲荷駅 
伏見稲荷駅
伏見稲荷大社は近くに駅があるので、参拝するには便利なロケーションです。
千本鳥居の先には、標高約233メートルの稲荷山があり、一周約4キロ、2時間ほどで回れるそうです。
ご利益のあるお社や見どころが随所にあり、お山めぐりを体験してこそ、伏見稲荷大社を知ることができるそうなので、次回チャレンジしてみたいと思います。
それでは、また。